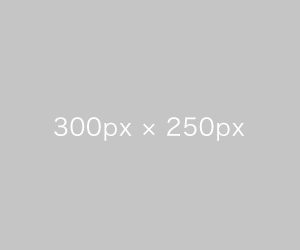先日、ユニークな経歴を持つ方々を深掘りする番組「ミラクルモンスター」に、驚くべきゲストが登場しました!それは、なんと元メジャーアーティストにして、現在は保育園の経営や様々な地域活動をされている當銘孝文さんです。
一体どんなお話が飛び出すのか、楽しみに伺いました。

社会福祉法人 がじまる福祉会 當銘孝文
https://www.instagram.com/tometakafumi/
幼少期から「自分で考える」少年時代
イ: 當銘さんの子供の頃を一言で表すと、どのようなお子さんでしたか?
當銘さん: 「生意気」だったそうです。実家が保育園だったため、広い庭にある大きなガジュマルを遊び場に、親の道具を使って自分たちでブランコや秘密基地を作る、まさに「ジャイアン気質」の子供でした。小学校に入ってからは、先生の矛盾を感じて教科書を閉じ、独学で勉強を進めた経験も。授業中は違う科目の教科書を開いていたそうです。 この経験から、「自分で考える」「自分で楽しみを見つけて課題を解決するのが楽しい」と思えるようになったことが、今の活動に繋がっていると感じているそうです。勉強は嫌いにならなかったものの、「やれ」と言われるのが嫌いなタイプで、自分がやりたいことはいくらでもやりたい、という性分だったようです。
保育士を目指した意外なきっかけ、そしてメジャーデビューへ
イ: 當銘さんが保育士になろうと決めたのは、いつ頃、どのようなきっかけだったのでしょうか?
當銘さん: 中学校2年生の時でした。地元で一家心中事件があり、保育園を運営していたお母様が「うちに来たら働く場所もあるし、子供の面倒も見てあげられるのに」と話しているのを聞き、「保育園があれば、人の命を救えるかもしれない」と感じたのがきっかけです。
イ: そこからメジャーアーティストの道へ進まれたのは、またユニークな経緯ですね。
當銘さん: そして、「保育士になるんだったら、楽器の1つ2つ弾けなきゃいけないよな」と考え、ギターを始めたという、メジャーアーティストになった理由としては非常にユニークな背景がありました。音楽を始めてからは、「どうせやるならステージに立った方が上手くなる」→「ステージに立てるものならバンドだ」→「どうせやるならこうしたい」とどんどん深掘りしていき、いつの間にかファンがついてメジャーデビューに至ったそうです。 高校1年生からライブハウスでの活動や路上ライブを始め、スカバンド「スカしっぺ」として活動。当時のバンドブームもあり、オレンジレンジの事務所に誘われ、大学在学中にインディーズデビュー。大学卒業と同時に、バンド名を「オールジャパンゴイス」に変え、メジャーデビューを果たしました。
バンド活動中の葛藤と、保育士への強い思い
イ: メジャーデビューという華やかなキャリアを送りながらも、保育士への思いは持ち続けていらっしゃったのですね。
當銘さん: はい、中学校の頃に決めた「保育士になりたい」という思いがずっとありました。特に、地元の沖縄県での貧困問題などを聞くと、バンド活動に集中できず、「自分たちの音楽は何のためにあるんだろう」と悶々とする日々があったそうです。 この葛藤から、「音楽でできることには限界がある」と感じ、「子供たちのために直接できる仕事」として、やはり保育士を目指す気持ちが強くなりました。私にとって、世界一かっこいい仕事は音楽家よりも保育士であり、今でもそう思っています。
イ: バンド活動を終える決断は、どのようにされたのですか?
當銘さん: メジャーデビュー時に「2年だけやる」という約束をしていたこともあり、25歳になる年にバンド活動を終えることを決断しました。事務所との間では相当揉めたそうですが、「2年という約束だった」と貫き、保育士の道へ進みました。
保育士への転身、地域活動、そして経営へ
イ: バンドを辞められた後、保育士になるまでの道のりについて教えてください。
當銘さん: バンドを辞めた後、お金を貯めて沖縄女子短期大学へ。実家の保育園で事務員として働き始めますが、手取りが8万円だったことに衝撃を受けます。学校に通いながら土日はコールセンターでアルバイトをするなど、休みなしの生活を送った経験も。
イ: 保育士資格を取得された後、給与面での課題意識から活動を始められたそうですね。
當銘さん: 保育士資格を取得し現場に出た後も、給料の低さに疑問を感じ、「なぜ世界一かっこいい仕事の評価が低いのか」と調べ始めました。国の基準が関わっていることに気づき、日本保育協会に入って保育士の給与や配置基準の改善を国に要望する活動を開始しました。
イ: 地域活動にも積極的に取り組んでいらっしゃるとか。
當銘さん: 地域活動は高校生の頃から行っており、大学時代に一度離れますが、地元に戻ってから再開しました。当初は一人でゴミ拾いを始め、仲間を増やし、小さなイベントから活動を広げていったそうです。
イ: そして、実家の保育園の経営にも関わるようになったのですね。
當銘さん: 実家の保育園の状況もあり、後継者として関わるようになり、発言権を得るために副園長に就任。その後、園長となり、糸満市だけでなく、神奈川県川崎市でも保育園を設立しました。これは、沖縄の保育が全国に負けていないことを示したかったことと、都市部と地方の保育を比較研究し、将来的な支援方法に繋げるための勉強という意味合いが大きかったそうです。現在は、法人全体の統括や人事などに携わっているとのことです。
當銘さんの保育観とやりがい、そして課題
イ: 當銘さんの保育園では、どのようなことを大切にされていますか?
當銘さん: 主体性を尊重しつつも、朝の会や整列など、ルールはしっかりと設けているそうです。子供たちには「なぜそうする必要があるのか」理由をきちんと伝え、納得感を大事にしています。子供たちに選択したり、決めたりする経験をたくさん積ませたいという思いが強くあります。
イ: 保育の仕事のやりがいは、どのような時に感じますか?
當銘さん: やはり卒園児の活躍を見たときだと言います。中には地元の企業で活躍したり、一流商社に入ったりする子もおり、彼らが地元を愛し、貢献しようとしている姿を見るのが嬉しいそうです。保育園は絶対安全基地であるべきであり、子供たちが「あの時先生たちが優しかった」という記憶や、「自分たちを認めてくれた場所や人がいた」という思い出を残してあげることが、最も重要だと考えています。
イ: 逆に、大変さや難しさを感じることはありますか?
當銘さん: 親御さんの多様な教育方針や、情報過多な時代における保護者の選択への対応、そして特に沖縄県における障害児や医療的ケア児への行政支援の専門性不足を課題として挙げています。川崎市では市民の保育や子育てへの意識が高く、支援が進んでいると感じており、その差を痛感しているようです。
未来への展望と「恩送り」の精神
イ: 當銘さんの活動のインスピレーションの源は何でしょうか?
當銘さん: 一つは、映画「ペイフォワード」だそうです。これは、自分が受けた恩を3倍にして返す、あるいは受けた恩を次の3人に渡すという考え方で、「これって沖縄的じゃないですか」と笑います。今の時代は「ありがた迷惑」なぐらい押してくるような「恩送り」が足りないと感じており、そして「土足で人の心の玄関をこじ開けるぐらいやる人が必要だ」と考えているそうです。愛があれば、その「うざさ」も許容できるはずだと。
イ: 今後の挑戦について教えてください。
當銘さん: 現在行っている活動をさらに根付かせること。そして、海外、特に新興国などの子供たちと関わることも視野に入れています。 さらに、政治へのチャレンジも考えているそうです。子供や保育、教育の専門家が政治に少ないと感じており、「いなければ自分でやる」という発想で、子供たちの代弁者となり得る人が増えるべきだと強く感じています。 また、地域活動と経済を結びつける活動も行っており、商工会の副会長を務めた経験から、経済を活性化させて儲けを生み出し、その収益を福祉に回すという「循環型」の活動を目指しています。福祉だけで儲けるのは難しいからこそ、経済界が儲けて、それを福祉に投資するという考えです。保育や教育は、未来に対する一番大きな投資であり、そこに投資しないと国は弱くなる、と危機感を抱いています。
最後に
イ: 當銘さんのお話は、保育士という職業への熱い思いはもちろん、メジャーアーティストとしての経験、地域への貢献、そして未来を見据えた活動に至るまで、非常に多岐にわたり、聴く者を惹きつけました。インタビューの中で終始感じられたのは、子供たち、そして地域への深い愛情と、「ないものは作る」「いなければ自分でやる」という強い主体性ですね。
當銘さん: 5月30日には、糸満ハーレーという伝統行事があり、優しくアヒル取りをする面白いイベントや、転覆バーレーなど迫力あるレースが見られるそうです。ぜひ糸満市にも足を運んでほしいとのことです。 私の今後の活動は、インスタグラムやFacebookで「當銘孝文」と検索すればチェックできるとのことです。
イ: 素晴らしいお話をありがとうございました!