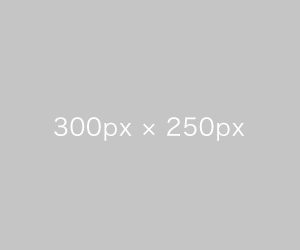はじめに
NPO法人Miraikanaiの番組「ミラクルモンスターミラモン」に、ゲストとして宮本二郎先生をお招きしました。宮本二郎先生は、小児緩和ケア訪問診療医としてご活躍されながら、沖縄県に「コミュニティ型こどもホスピス」を設立を目指す「NPO法人沖縄こどもホスピスのようなものプロジェクト」の代表理事も務めていらっしゃいます。今回は、先生のユニークなご経歴や、現在の活動にかける情熱について、深く掘り下げていきました。
宮本 二郎さんプロフィール
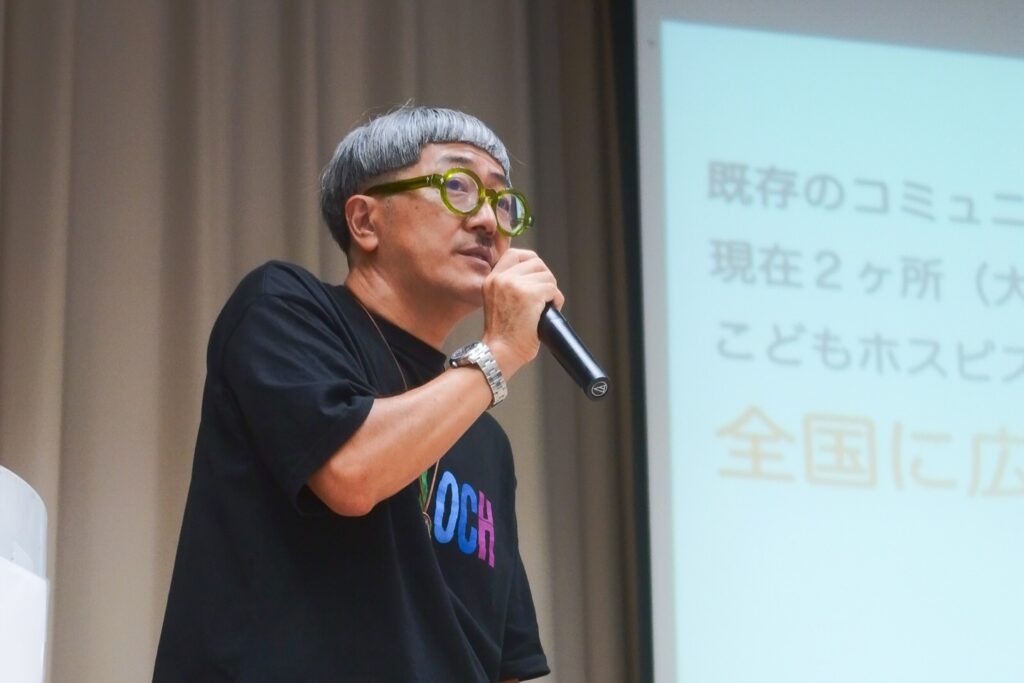
- 名前: 宮本 二郎(みやもと じろう)
- 現在の肩書き: 小児科医、小児緩和ケア訪問診療医、NPO法人沖縄こどもホスピスのようなものプロジェクト代表理事、Kukuruきっずクリニック小児科医
現在の主な活動:
- 小児科医、小児緩和ケア訪問診療医、Kukuruきっずクリニック小児科医として活躍されています。
- 特定非営利活動法人 沖縄こどもホスピスのようなものプロジェクト 代表理事を務めています。
◦ このプロジェクトは、沖縄県に「コミュニティ型こどもホスピス」を開設・運営することを通じて、すべての子どもたちの優しさとケアが循環するまちづくりを目的に活動しています。
◦ 主な取り組みとして、子どもとご家族への全人的ケアの提供、小児緩和ケアの普及啓発、コミュニティ型こどもホスピスの建設準備、優しさとケアが循環するまちづくりのためのイベント実施などが挙げられます。
イ:宮本二郎先生、本日はお越しいただきありがとうございます。まずは、幼い頃や学生時代についてお伺いしたいのですが、今の活動に繋がるような体験はありましたか?
宮本二郎:ありがとうございます。子供の時は、医者としての「体に興味がある」とか「人に良いことをしよう」という気持ちはあまりありませんでした。友達が多く、活発なタイプでしたが、喧嘩は弱かったですね。
都会での自然との触れ合いとプラモデル
宮本二郎:私は東京の赤羽出身で、都会の環境ではありましたが、そこら中で遊び回るのが大好きでした。特に虫が好きで、雑草のところにいるアリやカマキリ、バッタなどを観察していました。カマキリとバッタを戦わせる遊びもしていましたね。
イ:都会でそういった自然と触れ合われていたのですね。他にも印象的なエピソードはありますか?
宮本二郎:プラモデルのガンプラが流行っていた頃、みんなと同じように説明書通りに作ることができませんでした。部品が半分くらい余ってしまうこともあったのですが、自分なりの違うものを作っていました。当時はコンプレックスでしたが、大人になって幼馴染から「あれは羨ましかった」と言われて、少し驚きましたね。
イ:自分なりのストーリーを重視するというのは、今の活動にも通じる部分がありますね。高校時代はどのような夢をお持ちでしたか?
高校時代の夢と進路選択
宮本二郎:高校時代は、音楽か落語の道に進みたいと考えていました。音楽センスがあったわけではないのですが、「そういう場所で過ごしていること自体がかっこいい」と思っていたんです。しかし、親からは「とりあえず薬剤師の免許を取ってから好きなことをやれ」と言われ、薬剤師の道へ進むことになりました。
イ:親御さんの意見で進路が変わったのですね。大学受験の際には何か印象的な出来事がありましたか?
宮本二郎:大学受験の締め切り前日に、家出をしたことがあります。お金も持たず、池袋でこれからどうしようかと考えていたら、自衛隊員に勧誘されまして。その場の雰囲気に恐怖を感じ、このままついて行ったら「戻ってこれない」と直感し、家に戻りました。正味10時間ほどの日帰り家出でしたね。
薬剤師から医師への転身

イ:壮絶な家出経験ですね!さて、社会に出て最初に就かれたお仕事は薬剤師だったと伺っています。どのような経験をされましたか?
宮本二郎:実家が薬局で、6歳上の兄も薬剤師でしたので、私は推薦入試(面接と小論文)で薬学部に進学しました。薬剤師の国家試験はしっかりと勉強して合格し、卒業後はドラッグストアで2年強勤務しました。そこで接客の基本を学び、お客様の話を聞きながら最適な薬を提案することに大きなやりがいを感じていました。
イ:充実した薬剤師生活だったように思いますが、なぜ医師を目指されたのですか?
宮本二郎:いくつかのモヤモヤがあったんです。例えば痔の薬を買い続ける若い女性患者さんに対して、もっと根本的な治療を提案できないことに違和感を覚えました。薬剤師は話を聞くことはできても、診察や検査、手術といった治療の選択肢が限られていて、一部のことしかできていないと感じたんです。もっと全体を見て治療できる医師になりたいと強く思うようになりました。
イ:それが大きな転機となったのですね。医師になるためにどのような努力をされたのですか?
宮本二郎:薬剤師を辞めて、2年間勉強に専念しました。27歳で国立大学の医学部に合格し、6年間の医学部教育を受けました。その後、2年間のスーパーローテート制度で内科、産婦人科、小児科、精神科など、一通りの科を経験しました。研修医の給料は以前は低くアルバイトが必要でしたが、私の頃には改善され、その代わりにアルバイトは禁止になりました。
小児科、そして緩和ケア医へ
イ:様々な科を経験された後、最終的に小児科を選ばれたのはなぜですか?
宮本二郎:医学部に入った時には、すでに子供が2人いました。一番上の長男は病弱で小児科によく通っていたのですが、その時の小児科医のぶっきらぼうな態度が許せなくて。親の目線で、もっと良い小児科医になりたいという思いがありました。また、学生時代に小児がんの実習が楽しかったこと、そして9歳で脳腫瘍で亡くなった甥っ子の存在が、この道に進むきっかけになったと後になって感じています。内科も選択肢にはありましたが、全体を見たいという思いから小児科を選びました。
イ:小児科専門医としてご活躍された後、小児緩和ケアの道に進まれたのはどのような経緯からでしょうか?
宮本二郎:小児科専門医の資格を取得した後、小児がんの治療に携わりました。その中で、治癒が難しい子どもたちのケアに深く関わるようになり、緩和ケアの必要性を強く感じたためです。
「正解がない」緩和ケアの難しさ
イ:緩和ケアの現場では、どのような大変さや難しさを感じますか?
宮本二郎:緩和ケアの世界には「正解がない」という難しさがあります。例えば、病気の子どもが「家に帰りたい」と願ったとして、それを叶えることが本当に最善なのか。家に帰しても、毎日看護師さんが来たり点滴を続けたりすることで、家が病院のようになってしまい、かえってゆっくり過ごせなくなったり、親御さんの負担が増えてピリピリしてしまったりする可能性もあります。
イ:子供の願いを叶えることが、必ずしも幸せに繋がるとは限らないのですね。
宮本二郎:そうです。どちらが良いのか、何が正しいのか分からない中で、常に最善の選択を模索し続けることが最も難しいと感じています。最終的に答えが分からずに終わることもありますが、それでも「良い何か」を見つけたいという思いで活動を続けています。また、緊急時には自身のプライベートよりも仕事を優先しなければならない大変さも感じています。しかし、患者さんやご家族との関わりの中で、空気が変わる瞬間に魅力を感じ、そこにやりがいを感じています。
NPO法人沖縄こどもホスピスのようなものプロジェクトの活動
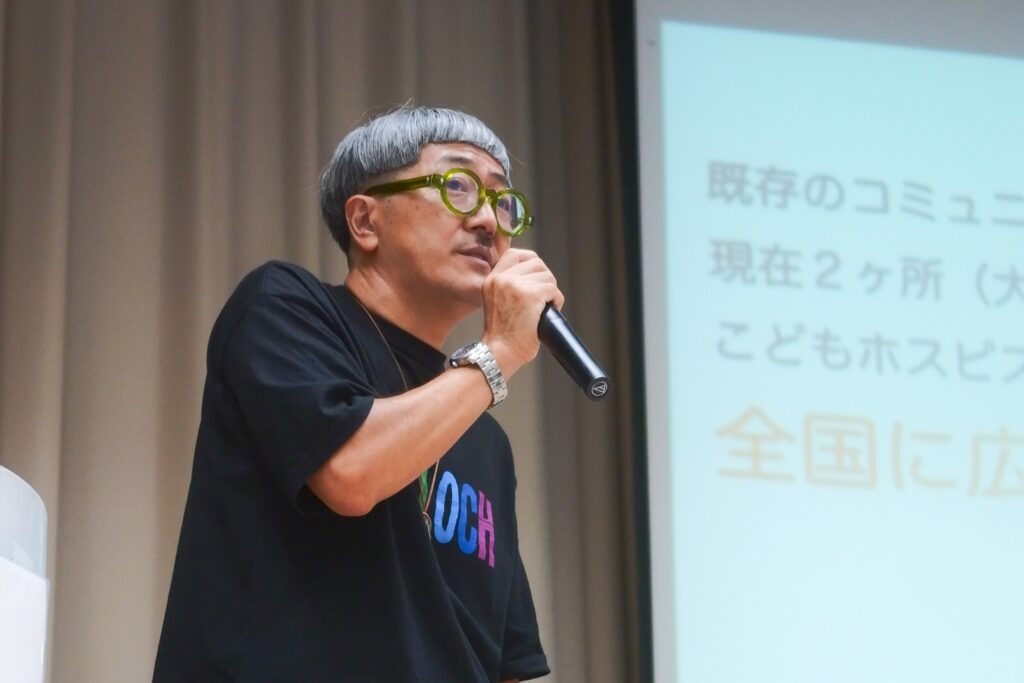
イ:現在、宮本先生は「NPO法人沖縄こどもホスピスのようなものプロジェクト」の代表理事を務めていらっしゃいますが、このプロジェクトについて詳しく教えていただけますか?
宮本二郎:はい、私たちは沖縄県に「地域型コミュニティ型こどもホスピス」を設立・運営することを目指して活動しています。これは、全ての子どもたちの「優しさとケアが循環するまちづくり」を目的としています。
イ:地域型こどもホスピスとは、具体的にどのような施設なのでしょうか?
宮本二郎:一般的な医療型ホスピスが診療報酬で運営される病院であるのに対し、地域型ホスピスは病院ではないタイプで、寄付や助成金で運営されます。病院は病気や怪我を治す場所なので、感染症対策や安静を保つために「あれもダメ、これもダメ」と制限が多くなります。しかし、命を脅かされている子どもたちにとって、様々な体験ができないことは非常に大きいと私は考えています。
イ:病院では難しい「体験」を重視するということですね。
宮本二郎:そうです。子どもは体験を通してどんどん成長します。成功しても失敗しても、その経験が成長に繋がるんです。私たちは、病院ではできなかったことを、医療機関ではない地域型ホスピスで提供し、子どもたちが子どもらしく遊び、学び、安らげる場を整えたいと考えています。現在、大阪と横浜に2箇所あり、全国で約10個のプロジェクトが進行中です。
プロジェクトの具体的な取り組み
イ:具体的な取り組みとしてはどのようなものがありますか?
宮本二郎:主に4つの取り組みがあります。
- 子どもとご家族への全人的ケアの提供: 子どもが遊び・学び・安らげる場を整え、今この瞬間を大切に過ごすことを応援しています。
- 小児緩和ケアの普及と啓発: 「知るケア、するケア、しないケア」という講演会を年に1回開催し、緩和ケアの正しい理解を広める活動をしています。
- コミュニティ型こどもホスピスの建設: 建設に向けた勉強会と資金集めを行っており、認定NPO法人化も目指しています。
- 優しさとケアが循環するまちづくり: 「優しさ」や「ケア」を育み、循環する社会を目指したイベントなども開催しています。
イ:講演会以外にも、子どもたちが自由に遊べる場所を提供されていると伺いました。
宮本二郎:はい。「ヒラトバ(開きながらも閉じている遊び場)」という、子どもたちが自由に遊び、五感を活かせる「実験の場」を運営しています。例えば2月には、音楽家を2人お招きして、子どもたちが音で遊んだり、大きな紙にみんなでベタベタ絵を描いたりするイベントを開催しました。沖縄の自然を活かした遊びを通して、五感を使う体験の良さを感じてもらいたいと思っています。
今後の展望とリスナーへのメッセージ
イ:宮本先生の今後の夢や目標について教えていただけますか?
宮本二郎:一番大きな夢は、沖縄にコミュニティ型こどもホスピスを作ることです。そのためには、建物を建てるための資金が必要ですので、寄付活動や認定NPO法人化を目指しています。
イ:直近のイベントのご予定はありますか?
宮本二郎:2025年9月7日(日)に開催される「スマイルアクションin沖縄」で、約15分ほどの講話を予定しています。プロジェクトのブースも出展しますので、ぜひお越しください。講話では、小児がんの子どもたちが治療を終えて学校に戻ってきた時に、周囲がどのように関われば良いかについてお話する予定です。会場はうるま市照間で、ヤクルトと卵のプレゼントもありますよ。
イ:宮本先生、本日は貴重なお話をありがとうございました!
宮本二郎:こちらこそ、ありがとうございました!
Youtubeチャンネルでは動画でご覧いただけます♪
NPO法人沖縄こどもホスピスのようなものプロジェクトについて
- 公式ウェブサイト https://posloch.okinawa/
- Instagram https://www.instagram.com/posloch.okinawa/
- Facebook Facebookページ
愛称は「ポスロッチ」ですが、検索の際は「沖縄こどもホスピスのようなものプロジェクト」で検索してください。Facebookが最も更新頻度が高いです。お問い合わせは chp.okinawa2022@gmail.com まで。
プロジェクトでは賛助会員を募集しています