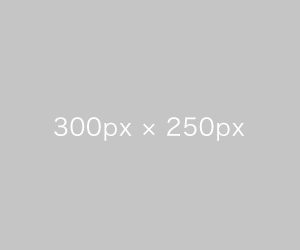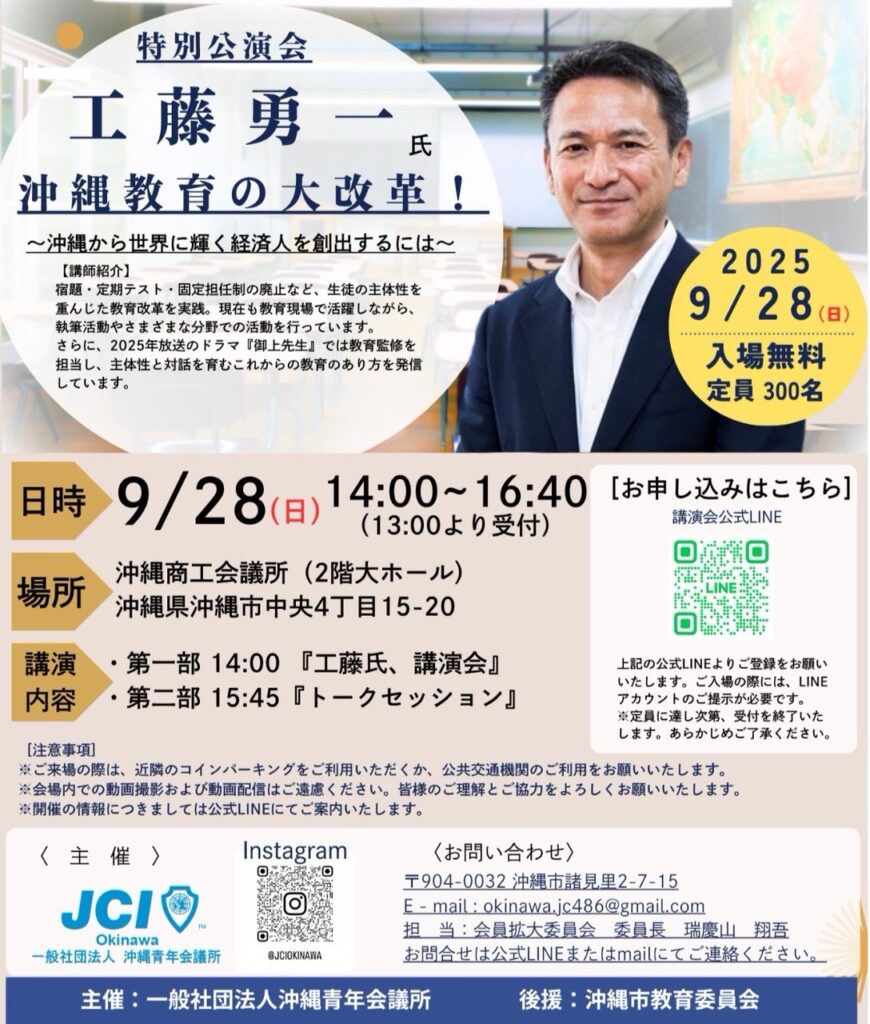
生きる力を育てる教育とは?
――大人が“手を出さず、手を放す”勇気
こんにちは。
理事長、ズケヤマセイラです。
今日は、工藤勇一さんの講演会に、たくま・あきのさん・ともこさんと一緒に参加してきました。
その学びをここにシェアしますね。
日本の教育と社会の現実
講演の冒頭、工藤さんは「日本の生産性はOECD加盟38か国中28位」と数字を示されました。
理由のひとつは、学校教育で子どもたちが「与えられたことをこなす」ことに慣れきってしまっているから。
明治から150年以上続いてきた教育は、
- 何を教えるか
- どう教えるか
この二つに重点が置かれ、「子どもがどう学ぶか」はあまり重視されてこなかったのです。
宿題と定期テストの落とし穴
特に印象的だったのが「宿題と定期テスト」の話でした。
宿題は「主体性を奪う象徴的な仕組み」だと工藤さんは言います。
子どもが「学びたい」と思う前に大人が課題を決めてしまう。
その結果、学びが“やらされ感”になってしまうのです。
定期テストも同じ。
「×を○にする作業」に追われて、点数を取ることが目的にすり替わってしまう。
本来の学びの喜びがどんどん失われていくのです。
「学習の目的が点数になった瞬間、子どもは学ぶ楽しさを失う」
この言葉には、会場のみんなが深くうなずいていました。
学び方は生き方につながる
教育のあり方は、そのまま将来の働き方につながります。
与えられた課題を効率よくこなす人材は育つけれど、
新しいものを生み出す力や、多様な人と協働する力は育ちにくい。
だからこそ「教える」から「学ぶ」へ。
- 主体的に問題を見つける力
- 対話的に学び合う力
これが、これからの社会に必要な力だと感じました。
生きる力を育てる3つの柱
OECDが提唱する「Learning Framework 2030」では、
教育が目指すべき柱として次の3つが示されています。
- 主体性 … 自ら考え、判断し、行動する力
- 当事者性 … 多様性を尊重し、対話で解決する力
- 創造性 … 新しい価値を生み出す力
知識の詰め込みではなく、人生を通して何度でも使える力。
それが「コンピテンシー(再現できる力)」です。
主体性を育てるには「心理的安全性」
主体性は「安心できる場」から育ちます。
- 自己決定できる環境(失敗が許される場)
- 脳をコントロールする力(メタ認知能力)
そのために、大人の問いかけが大事だと学びました。
「どうしたの?」
「君はどうしたいの?」
「何を支援してほしいの?」
また、結果ではなくプロセスを褒めること。
「努力すれば変われる」という感覚を、子どもに持たせてあげることができます。
メタ認知――自分の取扱説明書を持つ
人間は自分の脳を完全にコントロールすることはできません。
でも繰り返した行動がパターンをつくり、そのパターンを意識して変えることはできる。
これが「メタ認知能力」です。
ただの反省ではなく、自分の取扱説明書をつくって実行する力。
子どもがこの力を持てたら、失敗から立ち直る力がぐっと強くなりますね。
対立を上位概念で解決する
人はみんな違う考え方・感情・利害を持っています。
だから対立は自然なこと。
大切なのは、対立が起きたときに上位概念を探すこと。
- 兄弟げんか:「おもちゃを取られた」
→ 上位概念は「安心して遊びたい」 - 職場の意見対立
→ 上位概念は「より良い成果を出したい」
上位概念に立ち返れば、対立は協働へと変わります。
これが「パブリックリレーションズ」という、共通の目的を見つけ合意形成する力です。
大人の役割とは?
教育の本質は、大人が「どう手をかけるか」ではなく、
どう手を放すか にあります。
子どもが自ら課題を見つけ、挑戦し、失敗しながら学ぶ。
そのプロセスを尊重することこそが、「生きる力」を育てるのです。
今日のまとめ
- 日本や韓国は管理教育型、欧米は主体性重視型
- 宿題や定期テストは「やらされ感」を強め、主体性を奪う
- 主体性・当事者性・創造性がこれからの教育の柱
- 心理的安全性と自己決定の経験がカギ
- 対立は上位概念で解決する
- 教育は「どう関わるか」より「どう手を放すか」
今回の講演を通して、改めて思いました。
これからの教育に必要なのは、大人の勇気ある“ひと手放し”。
それが、子どもたちの未来の大きな一歩につながるのだと。